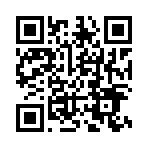2014年05月22日
義僕平八郎のこと

そもそもの発端は、元禄六年夏から秋にかけての遠三地方に於ける
熱病の流行にあり、当時天領白須賀宿は中泉代官所支配出張所管理
下に属していたが、出張所役人が横暴を極め、宿場人足に給与すべき
賃金の一部を十八年に亘って着服した。
貧窮にあえぎ流行に苦しむ人足らの窮状を見かねた平八郎の主人太郎
左衛門が、中泉代官に哀訴したことが仇となり、主人は勿論平八郎迄も
が獄舎に繋がれ、太郎左衛門の居宅・家財・田畑の悉くが没収された。
ほぼ半年にも及ぶ牢舎の明けが漸く終り、太郎左衛門と平八郎と身体だ
けは解き放たれたものの、住む家も無くその日の食事にも窮する有様で
あった。
こうした中で、平八郎はあちらこちら走り回って、半腐れ小屋を借り受ける
と、まず主人夫婦を住まわせ、自分は土間に藁を積み、その中にもぐり込
んで寝た。
また、魚や塩などの行商で得た僅かな利潤で主人夫婦を養った。
太郎左衛門は多年宿場の顔利きで、親戚も知人も多かったが、咎人であり
殊に代官役人に対する罪科であるだけに、誰もが役所をはばかって、同情
の手を差し延べては呉なかったし、夜逃げしたのでは、すぐさま無宿人とな
って、関所の通過ができないから、恥を忍び貧苦に喘いでも、その土地を離
れることはできなかった。
これは元禄十年(1697)秋ごろの事件で、それまで太郎左衛門は宿場の本陣
二家の一家であり、明応の大津波の直後、笠子原開拓に活躍した笠子七人
衆の筆頭者太郎左衛門の後裔で、代々白須賀宿の有力者であった。
また、平八郎は当時十八才くらいで、太郎左衛門の下男であった。
暫くたって、平八郎は単身江戸へ行くことにした。
この侭では何時まで経っても泣き寝入り以外何もできないと思ったからである。
行商で儲けた金は、一文残らず夫婦に生活費として渡した。
自分の懐は一文無しだから、見様見真似の按摩をしながら、それで路銀を稼
ぎ、心だけは一筋に、江戸への道をたどった。
やっとのことで江戸へたどり着いた平八郎は、ふとした事がきっかけとなり、
親切にしてあげた老人の口利きで、下町の豆腐屋に下働きとして住み込む
ことになった。
日々の仕事は楽ではなかったが、それ以上の苦労に堪え抜いた平八郎には
大したことではなく、豆腐屋の主人夫婦も働き者の平八郎がすぐ気に入って
大喜びであったが、平八郎の旧主の無実を晴らそうとする志は、些かも薄れ
ることはなかった。
平八郎は決死の覚悟で、老中秋元但馬守に駕篭訴を決行した。
それは、道端に平伏していて、高位高官の人の御駕篭が目の前に来たとき、
急に這い出て直訴することであり、正規の手順を経ない駕篭訴そのものを
犯罪とした時代であったから、訴えた者は死罪となる場合が多かった。
幸福の女神は思いも掛けず平八郎にほほえみかけて呉れた。
実は十何年も前に、平八郎は白須賀で秋元様に駕篭訴したことがあった。
殿様はその時のことを記憶して居られ、平八郎は微罪釈放となった。
遂にお取調べとなり、赤坂役人の非道は悉く曝露して免職となり、旧主太郎
左衛門は青天白日の身に還った。
時に正徳五年(1715)も暮れ近く、元禄以来二十三年もの長い歳月が過ぎて
いた。
この実話は新井白石が取り上げ、その著に記述したことから有名になった。
平八郎や太郎左衛門夫妻がその後どのように終わったかはわからないが、
白須賀本陣は元の二軒には戻らず、庄左衛門家一軒だけが、明治維新まで
続いている。
※参考文献:「湖北・湖西の民話と史話101話」より
Posted by 鈴木@SHOPS案内人 at 20:11│Comments(0)
│★南浜名湖の民話