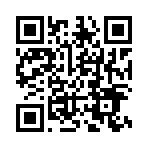2014年05月21日
海底からご出現の観音さま(後編)

(蔵法寺 潮見観音像)
聖観音ご出現から五十四年が経過して、宝永四年(1707)十月四日の
ことであった。
東海地方一円の大地震があり、これに伴って大津波が発生した。
この津波のために、白須賀・荒井・舞坂の各宿場を始め、当時海岸に
在った魚村の悉くが洗い流され、殆ど潰滅的な大惨事を受けた。
然し、汐見坂の中腹あった観音堂には、何の被害もなかった。
その前後、即ち十月三日の夜、白須賀宿の本陣大村庄左衛門方に
ご宿泊のお大名があった。

備前岡山三十一万五千石の殿様池田綱政公で、ご就寝早々観世
観音菩薩が夢枕にお立ちになり、その御告げは「大難ありそなたの
身辺に迫る。
早々にこの地を去れ」とのお指図でお殿様はその夢が余りにはっき
りしていて、しかもしきりに胸騒ぎもするので、夜中ではあったが、
すぐに宿直の侍に命じてお供の老職を呼ばせ、この話をなさると、
不思議な事に、老職も殆ど同じ夢を見ていた。

池田候は参勤交代明けの岡山帰城の途上であり、西国屈指の大々名
で、御供の人数も三百人近く、宿場中の宿屋だけでは入り切れないの
で、軽輩は民家に分宿していたから「明朝は早立ち」のお触れに、宿場中
が大騒ぎとなった。
十月四日の昼近く、お行列の後尾が漸く汐見坂を登り切った頃、突如と
して大地震が突発した。
有名な宝永の大地震がそれであった。

今から三百年近い昔のことであるから、その激震をマグニチュードで測る
すべは無いが、どの記録も筆を揃えたように「前古未曾有」と記している。
そして道路には稲妻の様に割れ目が走り、濛々と土煙が立ち、各所で崖
が崩れ落ちた。
空を飛ぶ鳥はみな地に降り、人々は歩行が出来ず、真青な顔をして身近の
大木にしがみつき、口は利けず、ただおろおろと震えてる外はなかったと記
される。
この大難にも、早立ちの御蔭で、何一つ被害のなかった岡山の殿様は、こ帰
国早々城内に慈眼堂を建てて観世音を祀り「白須賀観音」と名付けられた。
また汐見観音へのご報謝として、黄金の灯籠一対を作らせ、ご家来に命じて
白須賀まで届けさせられたが、途中で手違いが生じ、蔵法寺へは届かなかった。
当初汐見坂のうないの松の傍にあった観音堂は、数回の改築後に明治の
初年となり、廃仏棄釈に依って寺の財政が困窮したため、御堂が腐朽しても
改築が出来ず、止むなく寺の本堂を仕切ってその場にお祀りし、現在に至っ
ている。
※参考文献:「湖北・湖西の民話と史話101話」より
Posted by 鈴木@SHOPS案内人 at 20:11│Comments(0)
│★南浜名湖の民話