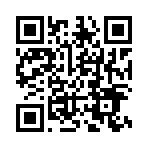2024年03月25日
家康公と等膳和尚出会いの原点、「篠島」

可睡斎という寺名の由来になった家康公と等膳和尚の出会い。
その原点となったのが「東海の松島」とも呼ばれる美しい景観の「篠島」です。
三河湾に浮かぶ篠島の歴史は古く、縄文・弥生時代の遺跡をはじめ、等膳和尚が住持
であった妙見斎跡の近くでは横穴式石室古墳も発見されてます。

大正10年(1921)に発行された「篠島史蹟」によれば、この島を訪れたのは、家康公
ばかりでなく、坂上田村麻呂、源頼朝、後村上天皇、加藤清正、西行法師などの名も
見られる。

中でも加藤清正は、名古屋城の築城に際して良質の石材を篠島に求め、海路と運河で
お城下まで運び、上へ行くほど急勾配になる「武者返し」の石組みで、難攻不落の城壁
を完成させた。
ちなみに等膳和尚の父親で海衆の五郎右衛門は島内の醫王寺に薬師堂を建立したが、
家康公はその志を良しとされ、苗字を与えられた。

その折、「どんな姓が望かと」聞かれたので、五郎右衛門は「然らば堅き姓を賜れた
なら幸せ」と申し上げたところ、家康公は「石橋」という苗字を与えられた。
篠島の石橋姓はこうして生まれ、現在もその子孫たちへと受け継がれている。