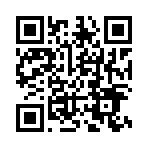2014年05月16日
海底からご出現の観音さま(前編)

承応三年(1654)三月十日の朝八時頃、いつも波荒い遠州灘が、この日に
限って珍しく凪いでいた。
漁師は朝が早い。
「お天気は上々、波は穏やか、これで大漁だったら、漁師ほどいい仕事は
ないなあ」などと、軽口を叩きながら手繰り寄せていた網が急に重くなった。
「おっしゃる通り、こりゃ大漁だぞ」一舟六人乗りの漁師達は、急に真顔に
なり網を手操る手許に、自然に力が入った。
果して魚網には沢山の鰯がかかっていて、果ては網の、目と言う目が無数
の鰯ばかりであったから、到底一人の力では手に負えず、六人総がかりで
全身汗まみれになって漸く網揚げが終わろうとしていたとき、「おい何か変な
物がひっかかっとるぞ」と、漁夫の一人に言われるまでもなく、すでに何人か
が気付いていた。
大あんばと呼ばれる網と袋の付け根の浮標あたりに、何か木の根のような
物がひっ懸っている。
「やあ、こりゃあ仏様だぞ」と言い合って、漁師らみんなが驚いた。
こうして、後日「汐見観音」と呼ばれる聖観世音菩薩の御木像が、蔵法寺前
の遠州灘の海底からご出現になった。
船頭伊三郎は信心の篤い人であったから、その日の漁はそこで打ち切り、
御仏像を家に持ち帰ると、真水で丁寧に洗い、真新しい晒布で巻いた。
いろいろ考えた結果、お寺の和尚さんの処へ持って行くことに決心すると、
すぐに組下の漁師を集め、その日の内に六人揃って蔵法寺へ持参した。
海からお出ましになった仏様を、漁師の家などに置いては勿体ないと思っ
たからであった。
その頃、曹洞宗竜谷山蔵法時は、白須賀宿は勿論遠州に名の通った大寺
であり、住職の明州韓察大和尚は、名僧としての聞こえが高かった。
和尚は伊三郎始め漁師たちのは話を聞くと、膝を叩いて喜びその労をねぎ
らった。
御仏像から早速巻いてあった晒を解くと、本堂のご本尊の如来様の脇に飾り
早速お供養の御経をよんだ。
御仏像は高さ約五十センチで一木彫、材質は不明、数多い御仏像の中で、
聖観音と申し上げる御像であることは前期の通りであります。
実はご出現の日まで、七日七夜に亘って、海が煌々と輝き、波の音も常と変
って、丁度天人が鼓を打つように聞こえたとのことで、それは一部の人たち
ではあったが、この変異は近々に何かお目出たいことのある前触れではな
いかと、話し合っていたとの事でした。
御仏像は両手で捧げてずっしりと重く、長い間海底に沈んでいたらしいが、厚
手の袋にでもお包みしてあったのか、寄生貝のいぼやぎ一つ付かず、全体の
御姿と言い、ふくよかな御顔と言い、何とも形容し難い気品が漂い、御目も
御口許も双の御耳も確かで疵一つなく、いずれ名のある古代の仏師が、精魂
を傾けて彫り上げた名品であろうと言うことになった。
やがて蔵法寺では仏像供養の大法要が挙行せられ、大和尚が中心となって
檀徒總代との相談の結果は、本堂から二百メートル程離れた汐見坂中腹の
うないの大松の傍に、新しく観音堂を建て、この御堂に安置してお祈りするこ
とになった。
そこからは海がよく見えるので「汐見観音」と言う御名のついたのもこの時か
であった。
また、貴いご仏像が海底からご出現に話が、次から次へと人々の噂に登り、
西遠から始まって、遠州一円に広がると、何時の間にか海上安全の仏様と
なり、漁獲豊漁の仏様だとの評判までも加わって、遠近から、殊に三河地方
からも、その御仏像をひと目おがみたいと、毎日毎日参詣客が押しかけ、
白須賀の宿場中が時ならぬお祭りのような賑やかさとなった。
汐見観音の別名が「帆下げ観音」とも呼ばれたのは、観音堂の沖を通る舟
が、帆柱の帆を一メートルほど下げて、敬意を表したことから、この名が通る
ようになったのだそうです。
お話は後編に続きます。
※参考文献:「湖北・湖西の民話と史話101話」より